はじめに―レッドリスト・レッドデータブックの概要
はじめに
このページでは、レッドリスト(RL)及びレッドデータブック(RDB)に掲載された動植物を分かりやすく紹介しています。ここに紹介した動植物は、今、日本のなかで生息地を失ったり、数が少なくなったりして、絶滅の危機にさらされているものです。
このページをご覧になって、どこに暮らす、どんな生きものが絶滅の危機にあるのかを知っていただければと思います。そしてこれらの動植物の絶滅のおそれがこれ以上深刻にならないようにするにはどうしたらいいか、考えてみてください。
ナゼ絶滅するの?
地球上にはさまざまな種類の野生生物が生息・生育しています。その数を正確につかむことはできませんが、500万とも5,000万とも言われています。これらの生物は、地球上に生命が誕生して以来、およそ40億年という永い進化の歴史のなかで生まれてきたものです。また、その進化の過程では、絶滅して地球上から姿を消してしまった生物ももちろんいます。恐竜は、もっとも分かりやすい、よく知られた例でしょう。このように、絶滅することも自然のプロセスなのです。
しかし、今日の絶滅は、こうした自然のプロセスとはまったく異なるものです。さまざまな人間活動の影響で、かつてない速さと規模で絶滅が進んでいます。森林伐採や埋め立てなどの開発による生息地の破壊や消滅、農薬などによる環境汚染、毛皮や牙、羽毛、そしてペットや鑑賞などを目的とした乱獲、元々いなかった生物(外来種)を持ち込んだことによる生態系被害や遺伝子汚染といった要因に加え、里山などでは、そこで暮らす人々の生活スタイルが変わってしまったために姿を消した生きものも数多くいます。
こうした原因が単独で、あるいはさまざまに重なり合って、今、多くの野生生物が絶滅の危機にさらされているのです。
レッドリスト・レッドデータブックとは
レッドリストとは、絶滅のおそれのある野生生物の種のリストです。これに対して、レッドデータブックとは、レッドリストの解説としてリストの掲載種の概要や生息状況等を記載し、編纂した資料です。レッドリスト及びレッドデータブックは、専門家による科学的・客観的評価により作成されています。レッドリストにより、絶滅のおそれのある野生生物を的確に把握することができ、また一般への理解を広げることができます。
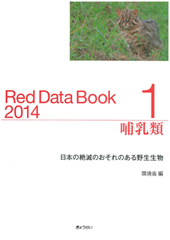
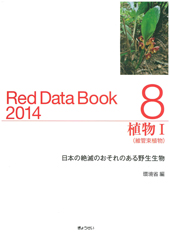
レッドデータブック2014(2014年~2015年刊行)
レッドリスト及びレッドデータブックは基礎的資料であり、リストへの掲載が捕獲規制等の直接的な法的効果を生むものではありませんが、社会への警鐘として広く一般に情報提供することにより、様々な場面で多様な活用が図られるものです。
※レッドリスト及びレッドデータブックにおいては、「絶滅のおそれのある種」は「掲載」または「評価」されるものであり、「指定」しているわけではありません。
動物では、①哺乳類 ②鳥類 ③爬虫類 ④両生類 ⑤汽水・淡水魚類 ⑥昆虫類 ⑦貝類 ⑧その他無脊椎動物(クモ形類、甲殻類等)の分類群ごとに、植物では、⑨植物Ⅰ(維管束植物)及び ⑩植物Ⅱ(維管束植物以外:蘚苔類、藻類、地衣類、菌類)の分類群ごとに、計10分類群について作成しています。
また、平成29(2017)年3月に新たに公表した海洋生物レッドリストでは、①魚類 ②サンゴ類 ③甲殻類 ④軟体動物(頭足類) ⑤その他無脊椎動物の分類群ごとに、計5分類群についてレッドリストを作成しています。なお、海洋生物については、平成29(2017)年7月現在ではレッドデータブックは作成していません。
さらに、環境省では次期レッドリストに当たる「第5次レッドリスト」の作成を進めており、令和7(2025)年3月に、①維管束植物、②蘚苔類、③藻類、④地衣類、⑤菌類の計5分類群について公表しました。他の分類群についても順次公表する予定です。なお、第5次レッドリストでは、上記のこれまでの陸域と海域のレッドリストを統合した上で一部の分類群を分割し、計16分類群のレッドリスト及びレッドデータブックを作成する予定です。
レッドリスト・レッドデータブックは、環境省以外に、水産庁、都道府県、NGO、学会等でも個別に作成されています。
野生生物の生息状況は常に変化しているため、レッドリスト・レッドデータブックにおける評価は、定期的に見直すことが不可欠です。
世界のレッドリスト・レッドデータブック
世界のレッドリスト・レッドデータブックとしては、国際自然保護連合(IUCN)という団体が、昭和41(1966)年に初めて発行しました。IUCNは、世界的な規模で絶滅のおそれのある野生生物を選定し、その生息状況を解説した書籍を発行しています。そのタイトルが「レッドデータブック(Red
Data
Book)」です。レッドという言葉は、例えばレッドカードやレッドゾーンなどのように、危険な、危機的なというイメージを連想させると思います。レッドデータブックも同様で、「危機的な状況にある生き物の本」というように理解すればいいでしょう。IUCNから発行された初期のレッドデータブックはルーズリーフ形式のもので、もっとも危機的なランク(Endangered)に選ばれた生物の解説は、赤い用紙に印刷されていました。
IUCNからは、レッドリスト・レッドデータブックの改訂版が順次発行されています。
The IUCN Red List of Threatened Species (英文)
http://www.redlist.org/
また、いくつかの国ではその国独自のレッドリスト・レッドデータブックが発行されています。
カテゴリー(ランク)の概要
| 絶滅(EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 | |
| 野生絶滅(EW) | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 | |
| 絶滅危惧種 | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している種 |
| -絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの | |
| -絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの | |
| 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅の危険が増大している種 | |
| 準絶滅危惧(NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 | |
| 情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 | |
| 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | 孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いもの |